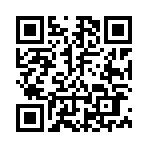2010年04月26日
4・25県民大会
米軍普天間飛行場の早期閉鎖・返還と、県内移設に反対し、国外・県外移設を求める『4・25県民大会』が読谷村で開催されました。
県内外からかけつけた参加者その数9万人超!


ギリギリまで参加を見合わせていた仲井真県知事も登壇し、県民一体となって基地撤去の意思を明確にしました。
沖縄に基地はいらない。そして、徳之島でもいらないと表明している。
基地のたらい回しは沖縄でも日本のどこの地域でもごめんです!!
国民の審判が下された鳩山政権は民意を受け止めて!
そして、アメリカ政府ではなく日本国民を、私たちの未来を守ってください!!
県内外からかけつけた参加者その数9万人超!
ギリギリまで参加を見合わせていた仲井真県知事も登壇し、県民一体となって基地撤去の意思を明確にしました。
沖縄に基地はいらない。そして、徳之島でもいらないと表明している。
基地のたらい回しは沖縄でも日本のどこの地域でもごめんです!!
国民の審判が下された鳩山政権は民意を受け止めて!
そして、アメリカ政府ではなく日本国民を、私たちの未来を守ってください!!
2010年02月25日
キラッと輝く看護めざして!
キラッと輝く看護めざして
2009年度卒後看護研究発表会
毎年恒例の卒後研究発表会が、2月17日(水)の14時~17時、沖協の講堂で行われ、1年目研修ナースは7演題、2年目研修ナースは6演題の13演題が発表されました。
4月に入職した時は、〝わからない、できない〟と不安だらけで泣きべそをかいていたのが、堂々と発表し、質問に答える姿に彼女等の成長が伺えました。プリセプター(新人看護師に一人ひとりにマンツーマンで振り当てられる担当の先輩のこと)からの心あたたまるお手紙もあり、感動的でした。

発表後は、08年卒の研修修了式を行い、当間智恵子県連看護委員長より8名の研修ナースへ2年間の研修修了証が渡されました。最後に、定年になる屋良看護部長から、研修ナースへの送る言葉を頂きました。お礼に研修ナースから屋良部長へメッセージが送られた内容を紹介します。
(沖縄民医連看護委員会 大城藤枝)

タグ :看護師
Posted by 沖縄民医連 at
14:15
│Comments(0)
2010年02月24日
「患者から学ぶ」こと
「患者から学ぶ」こと
沖縄健康企画事務交流集会
去る2月20日(土)、「患者から学ぶ社会保障制度」をテーマに中部協同病院地域連携室の新垣哲治さんを講師に招き、沖縄健康企画事務交流集会が開催されました。
日頃、薬局窓口にて直面する様々な困難事例(支払関連)は少なくありません。
そういった患者さんへの対応・相談をどのように行なったらよいのか?また自分たちには何ができるのか?が課題となっています。
今回の「事務交流集会」はそういった課題に取り組む職員の〝学びたい〟という思いのもと開かれました。
内容は『生活保護ついて』、制度の概や生活保護受給までの流れを事例を交えなら講演して頂きました。
患者さんが利用できる社会保障制度を学び、活かしていくことは、薬局窓口において患者と接する私たちにとって重要であることを改めて気付かされました。
講師からは、制度を学習することも大切であるが、患者さんと積極的に対話することが重要であることを教えてもらい、明日から役立てていきたいと思います。出来ることかではありますが、健康企画事務集団頑張ってます!(アピール!!)
(こくら虹薬局 金城宏乃)
Posted by 沖縄民医連 at
17:43
│Comments(0)
2010年02月15日
誰もが安心して老いていけるように-
誰もが安心して老いていけるように-
広域連合へ請願書提出
沖縄民医連が加盟する県社保協(沖縄県社会福祉推進協議会)は県後期高齢者医療広域連合会に請願書を提出してきました。
これは2月9日に開催された定例の広域連合議会にあわせてのもので、請願項目は、
①保険料の大幅引き下げ
②短期証発行の中止、「留め置き(※)」の解消
③資格証の発行はするな
④新型インフルエンザワクチン接種希望高齢者への無料接種を!
の4項目です。
担当者との懇談の中で、「資格証の発行は考えていない、4月に予定していた保険料の引き上げは今回は見送る」とのことでした。
しかし、そもそもこの制度は高齢者を差別し、大きな負担を強いる、いわゆる「姥捨て山」といわれる制度です。総選挙で民主党はマニフェストに制度の廃止を掲げて政権を取ったにもかかわらず、「4年内の新制度」へと方針転換し、国民の失望をかっています。
一日も早くこの制度は廃止させていく取り組みが必要です。「即後期高齢者医療制度は廃止せよ」の新しい署名用紙もできました。
長引かせるほど高齢者の痛みは大きくなります。祖父母、親、そして私たち国民誰もが安心して老いていける世の中にしていきましょう。
(※)留め置き:保険料の滞納があると効期限が2カ月の短期証が発行されるが郵送せず役所に来ないと本人にあげない
(沖縄民医連事務局次長 比嘉義信)
2010年02月04日
健診者の喜びがエネルギーに!
健診者の喜びがエネルギーに!
とよみ生協病院健診センターリニューアルしました★

健診センターという名称に、職員の皆さんはまだ「なに??」ではないでしょうか。
プレハブ棟の健診室での健診が頭に浮かぶのではないでしょうか。
職員一同心待ちにしていた健診センターが本館1階に移動してから一カ月が経ちました。
組合員の皆様や健診者の皆様から、広くゆったりとしたスペースで喜びの声が多く聞かれています。
今後の課題は、健診者の喜びの声がエネルギーとなり、前進することができると確信しています。
医療生協の皆さんには、定期健康診断(職員健診)の際見学して頂き、組合員の皆様や友人・知人を誘って年1回の健診で、安心した生活を送っていただきたいと思います。リニューアルした健診センターをやる気のエネルギーに変え、職員一同がんばります!!
(とよみ生協病院健診センター 運天節子)


2010年02月04日
完璧はない!だから・・・注意が必要!
完璧はない!だから・・・注意が必要!
九沖地協医療安全交流集会
去る1月31日(日)、福岡で医療安全交流集会が開催されました。
沖縄から6名、全体では114名の参加となりました。午前中は長谷川剛教授の〝医療における危機管理とコミュニケーション〟について記念講演を聴き、午後はボランティアの方々の模擬患者・家族役のリアリティー溢れたロールプレイを2事例実施し、質疑、感想等全体の意見交換の場としました。最後は、医師部門・安全管理部門・感染部門の分科会を実施し、交流を深め一日を終えました。
〝知らせたいこと〟は、より安全という状態はあっても完全な安全という状態はありません。ある対策を実施しても、必ずその裏側をかくような事例が発生します。完璧な対策はありません。
人は矛盾があっても自分が良いように解釈、実施する傾向があります。また、同じ物を見ても違う認識をすることもあるので、私達は(個々人)絶えず自分たちの行っている行動・行為の危険な面を把握しながら、注意深い医療を行っていく必要があると言うことです。
(沖縄協同病院・医療安全管理室RM 荷川取直美)
2010年01月06日
憲法が生かされる新しい時代へ
憲法が生かされる新しい時代へ
新年あけましておめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。
昨年は戦後50年余り続いた自民党政治が終わり、政治の大きな変革の時代が始まりました。新年を迎えるに当たり、皆さんはどのような希望を抱き決意をされたでしょうか。
今年は基地問題、格差と貧困を解消する社会保障のたたかい、民医連運動、県連の医療活動でも大きな変革と運動の前進が求められる年になります。大いに学び、活動して各事業所が大きく前進する年にしたいと思います。
新年早々、1月24日には名護市長選挙が行われます。新基地建設を許さないたたかいで最大の山場になります。稲嶺ススム統一候補の勝利をどうしても勝ち取らねばなりません。民医連と医生協労組の二者協は全力を尽くす必要があります。夏の参議院選や11月の知事選も政治革新にとって重要な選挙となります。
2月には全日本民医連の第39期の総会が開かれます。民主党を中心とした政権下で新たなたたかいが必要です。格差と貧困の改善に向けて、社会保障を充実させる運動方針や少子高齢社会の疾病構造の変化を踏まえた運動方針案が提起されます。また、民医連運動の更なる前進を指し示す綱領改定も提案されています。今後10年を見通した医療活動方針になっています。
新沖縄協同病院の医療活動も2年目になり、医療活動の前進と経営の改善が求められています。とよみ生協病院の改装オープンと透析患者会のみなさんの要求もある透析医療の改善方向性も必要です。すべての事業所で民医連方針に添った方針つくりが求められています。特に医師はじめ看護師の獲得と後継者育成は、今後の医療活動にとっては最重要な課題になります。3次長計の課題で名護への診療所建設も医師不足で困難な面もありますが、名護をはじめ北部地域の組合員さんの期待も大きい中、是非医師集団の知恵を出し合い成功させましょう。
この1年のたたかいは、今後の国のあり方を問う年になりそうです。憲法25条が生かされた医療・介護・福祉をはじめ、憲法9条が尊重される平和な国づくりにも全力を尽くそうではありませんか。
全職員の奮闘を期待しまして新年のあいさつにかえます。
(沖縄民医連会長 新垣安男)
2009年12月29日
反貧困・自立支援テント村
反貧困・自立支援テント村
いのちの平等程遠く・・・
去る12月26日(土)、那覇市与儀公園において反失業・反貧困沖縄県ネットワークと県生活と健康を守る会連合会の共催で「自立支援テント村」を設営し、同公園で暮らすホームレスや周辺に住む低年金高齢者ら約150人が相談に訪れました。全国各地で取り組まれている「テント村」の設営が県内で行われるのは初めてで、参加者は温かい豚汁を味わったほか、「仕事がない」「家がない」「国保税を滞納している」など、直面している厳しい実態を相談。民医連からも新垣安男会長ほか多数の職員が参加し、健康相談や配食などを行いました。中には、5日間食事をとっておらずふらふらな状態で訪れる人もおり、早急に生活保護申請するなど行政に繋げるべき事例も多く、深刻な社会情勢が浮き彫りになりました。当日参加した職員の感想を掲載します。(琉球新報より記事抜粋)

今回のテント村を通して、いろいろなことを勉強させてもらいました。普段は病院内で仕事をしているので、病院に来られた患者さんの対応をさせてもらっています。テント村に来られた方は気軽に健康チェッ
クをしたいだけの方もいらっしゃいましたが、中には「病院で診察してもらいたいが、お金がなくてできない」「以前に手術が必要だといわれたが、病院に行けないので放置した状態」というように、医療の恩恵を全く受けることができない人たちを、わずかの間に多く目の当たりにしたことが衝撃でした。
当日の与儀公園は天気も悪く肌寒い天気でした。温暖な沖縄ではありますが、これからは冬も真っ盛りになってきますので、居宅を持たない人たちの健康状態がとても心配になります。
また、生活保護や保険についても質問されましたが、自分の勉強不足で知らないことが多く、力になれなかったのがとても残念でした。テント村に来られた方々には、医療サービスだけでなく保険制度や法律的な面など多方面での教育の必要性も感じました。
今回のテント村での経験を通して「平等な医療」はまだまだ程遠いと感じました。現在揺れ動いている
医療制度ですが、このような人たちにも医療がもっと身近になる日が早く訪れて欲しいと思いました。
(沖縄協同病院1年目研修医 城間淳)
テント村では、食事の提供だけではなく、健康チェックや相談会などを行っていました。予想を上回る方が集まり、追加して豚汁を作っていました。夫婦と思われる2人がテントの方に歩いてきたので声をかけたところ「お金はいくらね?」と返ってきました。お金はかからないことを説明すると表情が緩み、「2つお願いね」と言われました。正直、私はこのやりとりに戸惑いを感じました。普通、食事をするときにはお金が必要になります。そのお金がなければ食べれなくて当たり前の現実があります。そのことに対し、私は特に何も感じたことはありませんでした。
しかし、十分なお金がなく、食事をとることもままならない方がこんなにも身近にいるんだなと実感しました。その場だけでの温かさだけではなく、常時安心して休める場所が必要なんだと感じました。今後、このような支援がますます必要になってくると思いました。
(沖縄協同病院リハビリ室 H)
2009年12月03日
平和を訴え本島縦断(第10回自転車平和リレー)
平和を訴え本島縦断
(第10回自転車平和リレー)
去る11月27日から29日までの3日間、沖縄青年ジャンボリ―(JB)と沖縄医療生協労組青年部(ACT)共催の『第10回自転車平和リレー』を開催しました。

開催にあたり、事前にスポンサーの呼びかけをさせていただき、部署・個人から140口もの支援があり、多くの方に協力していただきました。
また、出発式に沖縄民医連事務局から比嘉義信次長、沖縄い政教労組執行委員長の仲間美恵子さんから激励のあいさつを頂き、途中、内間事務局長も自転車をこぎ、閉会式には沖縄協同病院の比嘉努事務長が出迎えて激励と労いの言葉を頂くなど、記念開催にふさわしいものとなりました。また、全日本民医連新聞記者の佐久功さんも全日程参加していただき、全国へのアピールも行うことができました。
今回の自転車リレーでは、学習会を充実させたいという目的でコースを変更し、学習会の数を増やして参加者全員で平和について考えることができるようにグループ学習を行いました。
自転車リレー中は天候も良く、延べ人数43名で東村高江から沖縄協同病院まで走ることができました。学習会の実施やグループ学習を行い、お互いの思い・考えを話し合うことができ、その中で徐々に参加者の団結力も強くなり、平和への思いが大きくなりました。
グループ学習の中で、中協から家族で参加した子供たちの「僕達も戦争が嫌いなので、みんなが仲良く生活できる沖縄になってほしいです」との平和に対する訴えは、大変感動しました。自転車平和リレーの最中、参加者に「平和とは?」という問いかけをしていました。その中で「子どもと遊ぶこと」や「おいしいものを食べること」「未来に残すべきもの」など、それぞれの平和への思いも聴くことができました。

このような平和への思いを繋げるためにも今後も自転車リレーを継続し、平和の輪を広げていきたいと思いました。
最後に、今回の自転車リレーのために協力していただいた高江・辺野古の現地の皆様、スポンサーの皆様には大変お世話になりました。ありがとうございした。
(第10回自転車平和リレー実行委員長 石川輝裕)
タグ :自転車平和リレー
2009年12月03日
救急専門医に合格!施設も☆
救急専門医に合格!施設も☆
皆さん、こんにちは。沖縄協同病院から井上比奈です。このたび9月13日に行われた救急専門医試験を受けてきました。
結果は、、、伊良波禎先生と井上比奈との両名ともが合格し!これで沖縄協同病院においては救急専門医が3名になりました。(もう一人は伊泊広二先生)いろいろとご配慮いただいた麻酔科の先生方はじめ質問させていただいた諸先生方、すべてのスタッフの皆々様にこの場を借りてご報告かたがた御礼申し上げます。
施設としても平成22年1月1日より3年間救急専門医認定施設(この施設で研修すれば専門医が取れますよ、
という施設)となりましたのであわせてご報告申し上げます。
11月からは気管挿管認定の実習や救急救命士の就業前実習も始まります。
あたたかく受け入れてください。ご協力をお願い申し上げます。
(沖縄協同病院医局 井上比奈)
2009年11月18日
介護の仕事が好き!だからこそ・・・
介護の仕事が好き!だからこそ・・・
現場の苦悩を知って!
介護の日行動
去る11月11日は「いい日、いい日、いい毎日、あったかい介護ありがとう」とのキャッチコピーで、介護の日に制定されています。
当日は14か所の事業所の介護職、その他の職種100名が集まり、パレットくもじ前で介護の現状をマイクリレーで訴えました。

各々の施設から「介護の仕事はきつい・汚い・危険の中で仕事している」「自分の子供が介護をしたいと言ってもこのままの現状ではやらせたくはない」「介護の仕事が好きだが、臨時なので正職で働きたい」「介護保険改定で利用料が高く、介護サービスが利用できない方も多くいる」と自分の言葉で訴え、介護従事者の処遇改善や介護保険改善を求めました。
また、署名活動では123筆集まり、介護相談コーナーも設置しました。
私達の願いは介護従事者の処遇改善(生活できる賃金)、オジー・オバーや障害者にやさしい社会になるようにということです。これからも声を上げて行動していきます。
(かりゆしの里 G)
2009年11月11日
県民総意は明確!
県民総意は明確!
辺野古への新基地建設と県内移設に反対する11・8県民大会
去る11月8日、『辺野古への新基地建設と県内移設に反対する11・8県民大会』が開催され、県内外から2万1千人が結集しました。
3者協(民医連・医療生協・労組)からバスを14台配置、多くの職員・組合員も参加しました。
各事業所の参加者感想を特集します。

新たな基地を県民は望んでいない!今回の大会で県民の真意は明確に示されたと感じます。新政権には米国に追従することなく、勇気と誠意ある決断を求めます。これ以上の負担を沖縄県民に強いるのは、絶対に許せません。また、県外から多くの参加者に感謝・感激しました。多くの仲間と共に決して屈する事なく闘っていきましょう。
(生協デイサービスとよみ Y)
この小さな沖縄に、これ以上軍事基地をつくってはならない。自然を壊してまで基地をつくる必要はないとの思いでいっぱいです。
人間の身勝手だけで二度と環境破壊を起こさないためにも、基地のたらい回しに頼らない、基地ははっきりいらないと言えるよう一人一人が自覚し、すぐには解決できない問題ですが、一歩一歩自分達の想いを訴え、行動を起こすことに意味があると思います。
(メディコープおきなわ M)
「基地の県内移設反対!」の声に賛同した県民大会に、かりゆしの里からは12名が参加しました。会場の外での参加となりましたが、交代ずつ会場に入り「県民の真意」を感じ取ることができました。沖縄から基地を全て失くすという大きな目標に向けて、これからも様々な活動に参加していきたいと思います。
(かりゆしの里 T)
子供と青空の下、あらためて平和や基地問題について話す事ができたので良かったです。子供達の将来のために一日でも早く基地が撤去される事を願い、民主党連立政権に対し公約実現を強く迫りたいと思います。
(首里協同クリニック A)
11・8県民大会は、歩くのが少し不自由な組合員さん3名と共に、会場近くの木陰で参加しました。スピーカーから聞こえる発言者の声と会場にいる参加者たちの拍手、ヤジ、声援など舞台が見えなくても会場の雰囲気そのままに体感できました。特に少年の訴えは強く心に響き、改めて基地の県内移設反対の声を政府に
届けねばと思いました。
(医療生協組織部 S)
今回、会場となった宜野湾市野外音楽堂に足を運んだのは、実に3年ぶりでした。確か当時は、私の大好きなミュージシャンの1人であるCoccoが、初めて沖縄でライヴをした時です。彼女はその時、「ひめゆり」の乙女たちのことを話してくれました。その翌年、今度は辺野古の海を題材にした「ジュゴンの見える丘」を発表しました。
11月8日、そこには確かに「平和」を愛して止まないうちな~んちゅの「心」がありました。世の中の流れが変わった「今」だからこそ、そのうちな~の「心」で、基地のない沖縄を実現できたら、という気持ちでいっぱいになりました。
(中部協同病院薬局 N)
2009年11月11日
高齢者複合施設オープン!
高齢者複合施設オープン!
安謝高齢者複合施設(1階 生協デイサービス安謝、2階 生協安謝ハウス)の開所式が10月10日(土)に行われました。地域組合員、理事の方、医療生協職員、合わせて約70名の方々の参加でした。
那覇支部あざみ班の幕開け「かぎやで風」で式が始まり、フラダンスに舞踊、最後にかりゆしの里職員による唄・三味線・太鼓で会場を華やかせ、素晴らしい開所式を挙げることができました。
参加者の多くが地域組合員さんで、待ちに待った自分たちの地域に新しい施設が誕生したと、大変喜んでいました。
10月12日から申し込みされている方々の入居が始まり、現在6人( 11月初旬には14名の満床になる予定)が入居されています。新しい環境に慣れずに、深夜も部屋に戻ってはまた廊下に出てきて、「私はいつ帰れるの?」「食事はいつ出るの…」など不安な表情でしたが、日ごとに環境に慣れ、職員とも意気投合し、ゆったりとした生活を送っています。
11月1日はデイサービスのオープンとなります(利用者募集中)。家庭的な雰囲気の中で、まずは安全・安心に過ごすこととして、機能訓練やレクなどで体力の維持を図り、和やかに生活が送れるように職員一同がんばります。
忙しい中、祝いに駆けつけて下さった職員の皆様、そして素敵なお花や鉢物を送っていただいた協同にじクリ、那覇民診、浦クリの皆様、会を盛り上げていただいたかりゆしの里の皆様に厚くお礼を申し上げます。
(安謝高齢者複合施設 所長大城貴子)
2009年09月28日
4項目要請請願署名の目標達成を目指そう!
4項目要請請願署名の目標達成を目指そう!
全事業所早朝決起集会
去る9月16日(水)、私たちがこの間要求を掲げ取り組んできた
「後期高齢者医療制度の廃止」
「生活保護世帯の母子加算手当の復活」
「障害者自立支援法廃止」
「利用者の負担を増やさず介護報酬の引き上げを」
などの要求を今すぐに実行せよと、新政権に求める「4項目緊急請願署名」を取り組む職員決起集会をおこないました。

沖縄協同病院では「病院玄関横コミュニティ広場」に県連職員やこくら虹薬局職員など約140名が結集し、県連アピールを読み上げ、全日本民医連会長声明を各部署で引き続き読み合わせをして頑張ろうと意思統一しました。
集会の中では、沖協平和社保委員長である上原昌義副院長も訴えをおこない、職員の頑張りに対する評価と困難な現状打開の為に管理部も全職員と団結して頑張ると意思表明し、署名などの取り組みに頑張ろうと訴えました。
その他に健康企画から上原代表取締役が患者の困難な事例を目のあたりにし、改めて民医連の職員が頑張る必要を述べました。
今回取り組む新署名は、民主党政権が選挙時に公約として掲げていた中身です。
私たちの要求と一致する今回の請願項目は誠意をもって実行してもらう事を署名を集め世論を盛り上げて強く求めていきましょう。沖縄協同病院職員は一人10筆を目標に取り組みを提起して準備をしています。
(沖縄協同病院事務次長 知念毅)
2009年09月15日
祝!救急医療功労者労働大臣表彰
祝!救急医療功労者労働大臣表彰
沖縄協同病院
沖縄協同病院が9月9日、平成21年度救急医療功労者厚生労働大臣表彰を受けることになり、東京で開催された授賞式に仲程正哲院長が参加しました。
今年度の受賞は全国から6団体と7医療機関、個人として22名となっています。
沖縄協同病院は全国の7医療機関での受賞となっており、沖縄県内では唯一の受賞となっています。残りの6医療機関は市立室蘭総合病院(北海道)、済生会福島総合病院(福島)、県立十日町病院(新潟)、姫路赤十字病院
(兵庫)、田上病院(長崎)、蘇陽病院(熊本)となっています。
授賞式には厚生大臣は選挙結果の影響なのか欠席だったそうですが、副大臣をはじめ厚生労働省の官僚が多く参加していたと報告がありました。
また、9月12日には那覇市救急・防災フェアにて那覇市の救急業務の重要性を深く認識し救急医療を推進、救急患者の人命救助に尽力し、また、救急隊員の技術の向上に貢献したということで感謝状をいただきました。
今後も地域医療を守り発展させるために全職員で頑張っていきます。
(沖縄協同病院事務次長 比嘉勉)
2009年09月15日
Yes,we can ノーモア核兵器!
Yes,we can ノーモア核兵器!
原爆資料展in沖縄協同病院
今週の9月14日(月)から18日(金)まで5日間の予定で、沖縄協同病院の正面玄関横の「コミュニティ広場」(芝生が生い茂っているスペース)にて、原爆資料展を開催しています。
主催は、沖縄民医連と沖縄協同病院・平和社保委員会です。
2010年におこなわれるNPT(核不拡散条約)再検討会議にむけて、現在取り組んでいる「核兵器のない世界を(国際署名)」の署名を大きく広げる事を目的にしています。
沖縄は米軍事基地に囲まれ、日常的に基地撤去のたたかいが行われていますが、今現在も全世界の人々が原爆の恐怖にさらされている現実を改善させる取り組みが弱い現実もあります。
多くの来院者に見にきて頂き、周りにも署名と核兵器廃絶の取り組みを広げて頂きたいと考えています。ご協力よろしくおねがいします。
↓「核兵器のない世界を(国際署名)」の署名にご協力ください。
http://www.antiatom.org/sig/2010/index.html
(沖縄協同病院事務次長 知念毅)
2009年09月12日
新型インフルエンザ、ヒブワクチンを公費助成で!
新型インフルエンザ対応、ヒブワクチンを公費助成で!
8月27日(木)、沖縄民医連も加盟団体となっている県社保協は、新型インフルエンザの対応と細菌性髄膜炎を予防するヒブワクチンの公費助成を求める要請を那覇市長あてに行いました。

『新型インフルエンザの対応』では、「那覇市では保険証の未交付世帯が約4000世帯存在している」ことが分かり、「この未交付世帯への受診抑制にならないように」保険証の交付を求めました。
また、無保険状態の方たちへの保険証発行について市当局は「公平感を持たせていきたい」と述べ、「ホームレスへの受診機会の確保」については、ホームレス支援対策をおこなっている「福祉政策課と調整をしていきたいと」述べました。
『細菌性髄膜炎の予防をするヒブワクチンの公費助成』については「重要性は認識している。今後、調査、研究していきたい」とし、「乳幼児医療費無料化などへの対応もあるので、そうしたものと整合性を持たせていきたい」と答えました。
県社保協の新垣安男会長はじめ6名が参加、沖縄協同病院・小児科医の嘉数健二医師も「ヒブワクチン」の有効性と細菌性髄膜炎の危険性などを説明し、「早期に実現できるように」と強く要請しました。
県社保協が那覇市へ要請
8月27日(木)、沖縄民医連も加盟団体となっている県社保協は、新型インフルエンザの対応と細菌性髄膜炎を予防するヒブワクチンの公費助成を求める要請を那覇市長あてに行いました。
『新型インフルエンザの対応』では、「那覇市では保険証の未交付世帯が約4000世帯存在している」ことが分かり、「この未交付世帯への受診抑制にならないように」保険証の交付を求めました。
また、無保険状態の方たちへの保険証発行について市当局は「公平感を持たせていきたい」と述べ、「ホームレスへの受診機会の確保」については、ホームレス支援対策をおこなっている「福祉政策課と調整をしていきたいと」述べました。
『細菌性髄膜炎の予防をするヒブワクチンの公費助成』については「重要性は認識している。今後、調査、研究していきたい」とし、「乳幼児医療費無料化などへの対応もあるので、そうしたものと整合性を持たせていきたい」と答えました。
県社保協の新垣安男会長はじめ6名が参加、沖縄協同病院・小児科医の嘉数健二医師も「ヒブワクチン」の有効性と細菌性髄膜炎の危険性などを説明し、「早期に実現できるように」と強く要請しました。
(沖縄民医連事務局 新垣潔)
2009年08月28日
沖縄医療生協初の!
沖縄医療生協初の
「介護の社会化」をめざしスタートした、介護保険制度は10年目を迎えました。
しかし、「保険あって介護なし」の現実が一層広がっています。
高齢者を取り巻く環境はどんどん厳しくなり地域のニーズに充分対応できる状況には至っていません。「退院するよう言われたが行き場がない」「施設入所も待機まち」「要支援になったので施設や有料老人ホームから出るように言われたが在宅では不安」等、相談が後をたたない状況です。
そんな中、在宅で安心して暮らし続ける基盤づくりとして、介護や居住性を備えた「住まいづくり」をすすめ、沖縄医療生協では初の高齢者複合施設が10月1 日安謝にオープン予定で、現在着々と工事が進められています。
この施設は1階に通所介護(生協デイサービス安謝)と厨房、2階は住宅型有料老人ホーム(生協安謝ハウス)となっています。
有料老人ホームは入居定員14名。基本的にはケアマネジャーの作成したプランに沿って介護保険のサービスを利用しながら家庭的な雰囲気のなか共同生活を送ります。24時間、介護職員が常駐し生活支援を行い、医療との連携も図りながら安心して過ごせるような支援をしていきます。
施設は閑静な住宅街の中にあり、地域の開かれた施設をめざし、隣近所、組合員がいつでも立ち寄って交流ができるような場所をめざします。
只今デイサービス利用者、ハウス入居者申し込み受付中です。
また、ハウスで働く介護職員も募集中です。隣近所、知人などおりましたら紹介してください。
デイサービス利用者、ハウス入居者申し込み、介護職員募集
【連絡先】
沖縄医療生協 介護事業部 大城貴子・城間愛子
☎098-856-3107
高齢者複合施設いよいよオープン!
「介護の社会化」をめざしスタートした、介護保険制度は10年目を迎えました。
しかし、「保険あって介護なし」の現実が一層広がっています。
高齢者を取り巻く環境はどんどん厳しくなり地域のニーズに充分対応できる状況には至っていません。「退院するよう言われたが行き場がない」「施設入所も待機まち」「要支援になったので施設や有料老人ホームから出るように言われたが在宅では不安」等、相談が後をたたない状況です。
そんな中、在宅で安心して暮らし続ける基盤づくりとして、介護や居住性を備えた「住まいづくり」をすすめ、沖縄医療生協では初の高齢者複合施設が10月1 日安謝にオープン予定で、現在着々と工事が進められています。
この施設は1階に通所介護(生協デイサービス安謝)と厨房、2階は住宅型有料老人ホーム(生協安謝ハウス)となっています。
有料老人ホームは入居定員14名。基本的にはケアマネジャーの作成したプランに沿って介護保険のサービスを利用しながら家庭的な雰囲気のなか共同生活を送ります。24時間、介護職員が常駐し生活支援を行い、医療との連携も図りながら安心して過ごせるような支援をしていきます。
施設は閑静な住宅街の中にあり、地域の開かれた施設をめざし、隣近所、組合員がいつでも立ち寄って交流ができるような場所をめざします。
只今デイサービス利用者、ハウス入居者申し込み受付中です。
また、ハウスで働く介護職員も募集中です。隣近所、知人などおりましたら紹介してください。
(医療生協本部介護事業部 OT)
デイサービス利用者、ハウス入居者申し込み、介護職員募集
【連絡先】
沖縄医療生協 介護事業部 大城貴子・城間愛子
☎098-856-3107
2009年08月13日
許すまじ「原爆」
’09原水爆禁止世界大会

◎今回特に印象に残っているのが、住職さんが言っていた言葉で「そこに銃があっても人は死なない。銃の引き金を引くのは人で、爆弾のボタンを押すのも人、戦争を起こすのも人。でも起こさないようにすることも人はできる。一人ひとりが自分に出来ることで、後世に伝えていくことが大切なんだ。」と言っていました。私も沖縄に帰り、自分の出来ることを考え、行動にうつしていけたらなと思います。
(かりゆしの里 AS)

◎協同病院で働いてから平和について考えることは増えましたが、その考えは沖縄規模だったと思います。それが今回の世界大会で、世界規模で平和について学ぶことができたと思います。また逆に沖縄での活動や現状をもっと全国にアピールする必要もあると感じました。この3日間、何度も何度も流れた「原爆許すまじ」という歌。この曲の歌詞が「アメリカ許すまじ」ではなく
「原爆許すまじ」というのが、復讐では何も生まれないこと、この世界が本当に平和になってほしかったという思いが強かったんだと思いました。悲しみや憎しみの連鎖が無くなり、世界が本当に平和になってほしいと心から思いました。
(沖縄協同病院6階病棟 NR)
2009年08月05日
認知症について学ぶ!
認知症について学ぶ!
介護事業所職員研修会
去る7月30日(木)介護事業所職員研修会が沖縄協同病院3階講堂で「BPSDの理解と対応」について浦添市にある城間クリニックの院長城間清剛先生を講師に86名の参加で行われました。
BPSDとは、認知症の行動と心理症状の略です。
まず認知症の種類と特徴について脳画像を見ながら細かい説明がありました。「老化による物忘れ」と「認知症の物忘れ」の違い、症状の説明では事例も取り入れながら話されていたため、普段私たちが接している利用者の方々と照らし合わせながら聞くことができ、より深く理解することができました。
自分の体の変調を言葉にできずトイレの失敗があり、何か気にかかること・理由があるから徘徊すること、それらを理解、把握するには日頃の観察や情報収集(バックグラウンド)が重要になります。
認知症の方の介護は、たとえ手を出さなくても目を離せないのが介護者の大きな負担にもなっています。家族の方々へ認知症の経過、今後の見通しを伝えるなどして介護の準備をしてもらうなど細かいケアも大切だと話されていました。
物忘れの失敗や今までできていた家事や仕事がうまくできないことを一番わかっているのは本人であること。不安と辛さでいっぱいであること。認知症の方が混乱するのは「自分が認知症になるなんて!」というやり場のない不安から悲しみや怒りからくる自然な反応であることをしっかり心がけて無理なく良い関係づくりをして本人が快適に過ごせるように関わっていきたいと気持ちを新たにもつことができた研修でした。
研修会参加者の感想に「今まで受けた認知症の研修の中で一番わかりやすかった」「講師の話口調や資料など非常に理解しやすかった」と大好評の研修会でした。
(沖縄医療生協本部介護事業部 OT)